協会のビジネスモデルとして人気があるのは、「養成講座」です。
協会を作り、その協会の名前で養成講座を開き、受講者(会員)を増やす。
養成講座ですから、講座を修了した人には資格を提供するのが普通です。
近年はこのビジネスモデルで協会を立ち上げる人が増えています。
とはいえ、養成講座であればどんな形でもよいかというと、必ずしもそうではありません。
協会の場合、いくつかタブーがあります。
今回はそのタブーについて解説します。
養成講座のタブー
講演と講座を混同する
カリスマ的な気質の人ほど、犯しやすい間違いの1つです。
講演と講座は、似ているようでまったく違うもの。
資格講座を実施する場合、ここを混同しないことが大切です。
映画でたとえると、
講演 =「タイタニック」
講座 =「ジュラシック・パーク」
となります。
どちらも大ヒットした映画ですが、両者には大きな違いがあります。
「タイタニック」といえば、俳優のレオナルド・デカプリオさんを思い浮かべる人が、多いのではないでしょうか。
「タイタニック」を観る人のうち、少なからずの割合の人がデカプリオさんを観ている。
ある意味、「タイタニック」はデカプリオさんを目立たせる映画だと言えるかもしれません。
「ジュラシック・パーク」の場合はどうでしょうか。
ジュラシック・パークの主役はあくまで恐竜です。
俳優を目立たせるための映画ではありませんでした。
「ジュラシック・パーク」を観る人は、大迫力の恐竜を観たくて映画館に来る。
俳優は恐竜を魅力的に見せるための、”道具”の1つでした。
この違いが、講演と講座の違いにそのまま当てはまります。
講演は、講演者が主役となります。
講座はそうではありません。
講座の主役はカリキュラムそのものであり、講師は主役ではなく、道具です。
この違いを理解せずに講演のような講座にしてしまうと、「ファンに楽しんでもらう講座」にはなるかもしれませんが、「養成講座」にはなりません。
教えたいことをだけを教える
情熱的な人ほど、犯しやすい間違いの1つです。
教える内容には
- (教える側が)教えたいこと
- (学ぶ側が)学びたいこと
- 資格保持者が知っておくべきこと
の3種類がありますが、このうちもっとも大切なのは3番目の「資格保持者が知っておくべきこと」です。
このことを意識してカリキュラムを組まなくてはなりません。
教えられることだけを教える
先生気質の人ほど、犯しやすい間違いの1つです。
「協会を作って養成講座をする」という言葉に対し、ついつい
自分が教壇に立つ姿
をイメージしてしまう人は、先生気質です。
自分が教壇に立つ前提でものを考える人は、
- 自分が教えられることは熱心に教えたい
- 自分の領域でないことは扱いたくない
これが悪いというわけではありません。
「○○先生から教わりたい」という需要もありますから。
けれども話が「養成講座」、しかも資格を提供する養成講座であれば、資格に必要とされる知識を、客観的に、過不足なく伝えることが何より大切です。
教えられることだけを教える、では、資格の目的を満たすことができません。
全部いちどに教える
サービス精神の旺盛な人ほど、犯しやすい間違いの1つです。
一般に、養成講座、しかも資格認定まで行う場合の受講料は、高くなります。
ついつい「高い受講料を払ってもらっているから、あれもこれも教えてあげたい」と考えてしまう気持ちは、わからないでもありません。
しかし、あれもこれも教えることに、あまりメリットはありません。
むしろ、
- 受講者側が消化できず、かえって不満につながる可能性があります。
- 資格認定に値するレベルに至らない可能性があります。
あれもこれも教えたいという気持ちが抑えきれない場合は、
初級講座→中級講座→上級講座
といった具合に、複数のレベル設定をするのがお勧めです。
1人で教える
仕事のできる人、会社感覚の強い人ほど、犯しやすい間違いの1つです。
自分1人でできる、そういう固定観念があるため、他の講師の力を借りようとしません。
「1人で教える」…これは、小学校の「クラス担任制」に似ています。
つい最近まで、日本の小学校は「クラス担任制」でした。
クラス担任の教員が、国語、算数、理科、社会…と、基本的にすべての科目を教えています。
この方式には限界があります。
クラス担任の能力を超える内容を教えることができません。
実際、「クラス担任制」が採用されているのは小学校だけです。
中学校以降は、「科目担任制(教科担任制)」となっています。
そのほうが、1人の教師の能力を超え、広く正確な知識を伝えることができるからです。
(なお、最近は学校でも科目担任制を導入する動きが見られます)

タブーに共通するもの
今回とりあげたタブーは、以下の5つです。
- 講演と講座を混同する
- 教えたいことをだけを教える
- 教えられることだけを教える
- 全部いちどに教える
- 1人で教える
この5項目に共通している要素は何でしょうか?
答は、2つあります。
1つは、
「個人の感覚・個人事業の感覚が抜けない」
です。
もう1つは、
「自分自身を主役に考えている」
です。
個人の感覚・個人事業の感覚が抜けない
協会でなければ、「個人の感覚・個人事業の感覚が抜けない」でもまったく問題ありません。
好きなことを、好きなようにやればよいからです。
しかし協会という舞台で養成講座をするのであれば、個人事業の感覚ではなく、団体の感覚で行う必要があります。
自分自身を主役に考えている
養成講座、中でもとくに資格講座は、受講者(会員)に協会のコンテンツを学んでもらい、資格を得て活動してもらうのが目的で行うものです。
前述した講演(映画でいうと「タイタニック」)とは目的が違います。
講座の主役はカリキュラムそのものであり、講師は主役ではなく、道具です。
ここをはき違えないようにしましょう。
まとめ
協会のビジネスモデルとして人気がある「養成講座」ですが、
- 個人の感覚・個人事業の感覚が抜けない
- 自分自身を主役に考えている
というメンタルを持ったまま養成講座をやってしまうと、間違えることになります。
その結果、やりがちな間違い(タブー)は、
- 講演と講座を混同する
- 教えたいことをだけを教える
- 教えられることだけを教える
- 全部いちどに教える
- 1人で教える
この5つです。






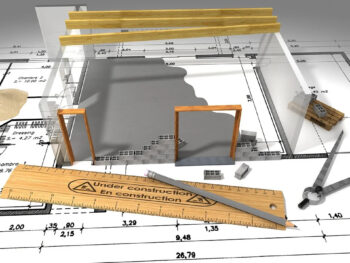

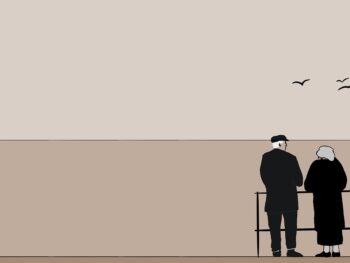





 協会という事業の特長
協会という事業の特長